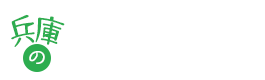将来の家族構成やライフスタイルの変化に備えて、早い段階から住まいにバリアフリーの工夫を取り入れる人が増えています。
2025年6月には、建築物のバリアフリー基準に関する改正政令が施行され、トイレ、駐車場、劇場等の客席についてより具体的で実用的な内容が示されました。
これにより、子育て期から高齢期まで、どのライフステージでも快適に過ごせる住まいづくりが推進されています。
そこで今回は、建築物のバリアフリー基準の改正動向と、日常生活を快適にする工夫、そして補助制度の活用方法についてご紹介します。
設計ガイドラインの記述強化で進む「標準化」
2025年の建築設計標準改正により、これまで「〜することが望ましい」という推奨表現にとどまっていたバリアフリー設計の記述が「〜する」という標準的な整備内容として強化され、建築設計において当然の配慮として位置付けられるようになりました。
建築物の設計では、トイレや浴室、玄関、廊下といった日常の動線上で、車いすやベビーカーの使用を前提とした設計が重視されています。一般的な住宅の廊下幅は78cm程度が最低限必要とされ、より快適な移動を考えるなら90〜120cmの確保が理想とされます。
また、玄関や浴室などの段差は極力なくし、スロープの勾配は建築基準法で1/8以下、バリアフリー法では1/12以下(屋外は1/15以下が望ましい)に抑えることが求められ、安全性と使いやすさの両立が図られています。
動線・仕様の工夫でより快適な生活へ
基準が整備された今、実際の暮らしに即した動線や仕様の工夫が重要となります。まず、各所に設ける手すりは、利用者の体格や使用目的に合わせて設置し、安心感を高めましょう。
さらに、滑りにくい床材を選ぶことで、転倒事故の予防にもつながります。また、移動がスムーズになるよう、生活空間を平屋やワンフロアにまとめる設計や、部屋を回遊できるような動線計画を取り入れると、日々のストレスが軽減されます。
引き戸の活用や、玄関スペースの広さ確保といった工夫も、将来の変化に対応しやすいポイントです。
まとめ:補助制度を味方につけて、安心の住まいづくりを
バリアフリー住宅は新築に限らず、リフォームでも実現可能です。2025年度は「子育てグリーン住宅支援事業」により、手すりの設置には5,000円、段差解消には7,000円、廊下幅等の拡張には28,000円といった補助が受けられる場合があります。
また、介護保険制度を活用したバリアフリーリフォームでは、一人あたり生涯で20万円(自己負担1〜3割)の補助が利用できます。
こうした制度を上手に活用することで、金銭的な負担を抑えつつ、自分たちの生活に合った機能を整えることができます。
将来を見据えて実例や設計案を比較検討し、安心して長く暮らせる住まいを形にしていきましょう。